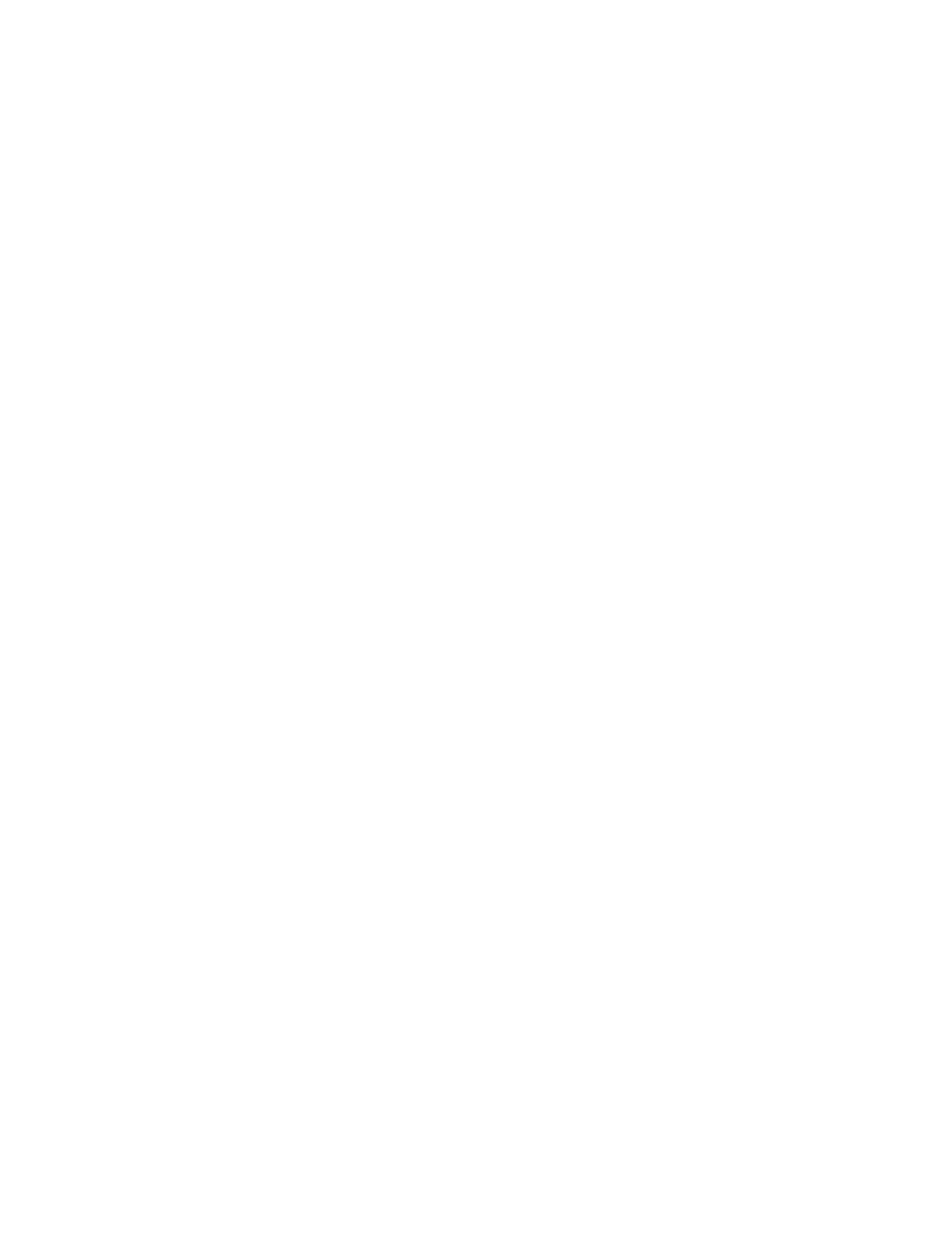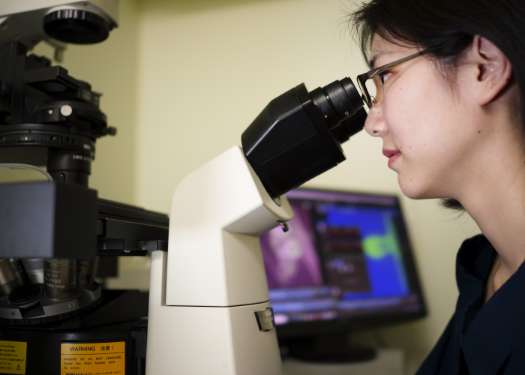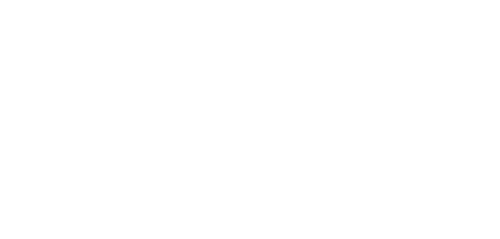世界をリードする
生命理学科
理学における生物学は実学ではありません。究極の目的は、生き物に対する何気ない見方を大きく変え、「生き物はああそうなんだ、そうしてできているのだ」と客観的な実感を伴って、生き物への新たな見方を提示することです。提示された世界が画期的であるほど、その結果は生物学の範疇にとどまらず、実学としても発展し、世の中を変えていくことでしょう。生命理学科は生物学科として創設されて以来、世界を先導する研究結果を生み出してきました。
「生き物を知りたい」― 秘めたる思いを持つみなさん、
生命理学科の教授陣とともに生物の理解を大きく切り拓き、世界の第一線へと羽ばたいてみませんか?
生命理学科が行う総合型選抜入学試験(令和8年度入学)
総合型選抜では、溢れ出る好奇心をもち、積極的に研究を立案主導し、その経験や結果を元にさらに何かをやり遂げたい、と強く感じているみなさんの応募を期待しています。その志と実績は以下のA-Hの科学コンテストなどにおける活動で示されるものと理解し、そこで優秀な成績を収めた方を対象とします(ただし令和6年度中に卒業した者及び令和7年度中に卒業見込みの者に限る)。この総合型選抜では大学入学共通テストは課しません。合格した場合に入学を確約できることも応募条件です。
国際学生科学技術フェア(ISEF)出場
日本学生科学賞(JSSA) 中央最終審査進出
高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC) 最終審査会進出
グローバルサイエンスキャンパス(GSC)全国受講生研究会発表会(サイエンスカンファレンス高校の部) 発表
名大MIRAI GSC 第3ステージ進出
名大みらい育成プロジェクト 第3ステージ進出
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会 全体発表(代表校選出)
上記以外の自由研究や課題研究で優れた発表を公的に証明できるもの
- 学校推薦型選抜とは対象者(出願資格・要件)が異なります。「部活動に打ち込んだ」は学校推薦型選抜としてありえますが、総合型選抜の応募理由にはなりません。学校推薦型選抜と異なり、令和6年度に高校を卒業した者でも応募できます。
生命理学科の魅力的な講義・演習・実習
世界最先端の研究の魅力
生命理学科には卒業研究ができる研究グループが20以上あります。質量分析計や次世代シークエンサーなどの先端機器を使い、分子構造やタンパク質機能など細胞内外の分子生理機能やゲノム解析をメインとして研究する研究室から、生物個体を使って細胞分裂や細胞の組織化などを研究する細胞生物学や発生、生理学、遺伝学の研究室、さらには行動、生殖、脳神経、生態などのより高度な生物現象の理解を目指す研究室などもあり、研究目的に適した生物を用いてさまざまな階層における研究が行われています。
植物系では、ホルモンと生存戦略、環境応答の分子機構、時空間解像度をもった細胞壁形成の解析、細胞集団運動の研究が行われており、動物系では、細胞分裂や細胞間・細胞内シグナル伝達の制御機構の解析、脳形成の仕組み、性決定と生殖多様性をもたらす分子機構の解明、行動や睡眠の神経回路機構、社会行動の進化などの研究が精力的に進められています。
また細胞系では、タンパク質安定制御機構の解明、転写翻訳の新たな理解の推進、細胞自身の形態形成解析、AIを用いた生物現象の定量的研究が行われています。
卒業生は、公的な研究機関や大学などのアカデミック分野で活躍するだけでなく、研究で培った科学的思考と理解力を基盤に世界の第一線で活躍しています。
それぞれの研究グループの詳細については「教員と研究活動」のページを確認してください。その中のリンク先で気になる研究室があれば入学後にコンタクトしてみると良いでしょう。大学1年生であっても、生物学や生物研究の詳しいところがわからなくても、研究室への訪問は歓迎してくれます。きっとテーマの魅力を丁寧に説明してくれるでしょう。
卒業研究テーマの例
- 寄生植物の発芽後の寄生プロセスにおける植物ホルモン作用の解明
- 植物の細胞壁は機械刺激を感知しカルシウムシグナルを誘導する
- 菅島近海由来の真菌の細胞分裂様式についての研究
- キイロショウジョウバエの歌識別学習を制御する神経機構
- 翅形成の力学的仕組みを説明する数理モデルの構築に向けて
- 透明魚を用いたアルツハイマー病病態解析のためのアッセイ系の開発
- メタボロームデータ解析による副腎偶発腫瘍の分類
- 新型コロナウイルスワクチン抗体動態を再現する数理モデルの開発
総合型選抜で入学することによるインセンティブ
- 【1】優先分属
-
理学部では2年生への進級時に学科を決定する学科分属が行われます。希望者が定員を超えた場合は学科により進学者が選抜されますが、本入試の合格者には生命理学科に優先的に進級する特典が与えられます。(注1)
- 【2】実技先取り研究室インターンシップ
-
理学部の1年時のカリキュラムは講義が中心となっており、実験技術を学ぶ実習は生命理学科の2年秋学期から履修します。本入試の合格者は希望に応じて1年次から研究室での短期~長期インターンシップを通じて高度な実験技術を学ぶ機会を得られます。(注2)
- 【3】生物学のプロフェッショナルに接する
-
研究者のセミナーや集中講義、卒業研究発表会を1年次から聴講する機会を得られます。これにより、教科書には書かれていない最先端の生物学を学び、プロの生物学の世界に接することができます。(注3)
- 【4】専属メンター制
-
生命理学科の教員が専属メンターに就き、勉強法や知識の深め方、進路などについて相談することができます。
- 生命理学科以外の学科を希望することも可能ですが、優先分属にはなりません。進級に必要な単位を取得できなかった場合は、本入試の合格者でも2年生に進級することはできません。
- 研究室の都合により希望する研究室で受け入れることができない場合があります。
- 主に授業期間外に開催されるセミナー等が対象です。
選抜方法と選抜スケジュール
提出された応募書類に基づいて第一次選考を行います。第二次選考では、名古屋大学理学部で午前中に研究発表を模した講義を受講していただきます。そして講義に関する小論文を執筆していただき、理解力や論理的な思考能力をはかります。午後は面接を実施します。小論文と面接の結果を総合的に評価し、最終的な選考を行います。
- 出願受付
-
2025年10月1日(水)~ 2025年10月6日(月)
- 一次審査
-
(書類選考)結果発表 10月24日(金)
- 二次審査
-
(講義に基づく小論文及び面接による選考) 11月8日(土)
- 合格発表
-
11月21日(金)
応募に際して準備すべき書類
- 入学志願票・写真票
- 研究報告書
- 志願理由書
- 志願者評価書
- 調査書
- 出願要件の確認書
- 任意提出書類(英語検定成績の提出が望ましい)
- 募集要項は下記で必ずご確認ください。
令和7年度 生命理学科 総合型選抜入学者プロフィール

高校在学時の研究
植物バイオマス利用のための前処理条件の検討
出身高校所在地:大阪府
高校3年時に履修した理科科目:生物、化学
高校在学時の研究
共食いによるプラナリアの記憶の伝達
出身高校所在地:埼玉県
高校3年時に履修した理科科目:生物、化学
高校在学時の研究
色素の可逆的光化学反応
出身高校所在地:埼玉県
高校3年時に履修した理科科目:物理、化学
高校在学時の研究
強磁性体における熱磁気効果
出身高校所在地:岐阜県
高校3年時に履修した理科科目:物理、化学
Q&A
必ずご一読ください
基礎学力はどの程度求められますか?
名古屋大学での講義を理解するため、そして第一線の研究へと学力を積み上げるために必要な基礎学力は必須です。名古屋大学理学部の一般選抜試験で合格する程度の主要5教科の基礎学力は必要でしょう。調査書や任意提出書類(Q2参照)、小論文や面接で評価していきます。
英語の検定試験を受けた結果を持っていますが、どのように提出すれば良いですか?
任意提出書類の一部としてください。実際に取ったスコア(もしくは級など)も任意提出書類に記載し、検定試験の結果のコピーを提出してください。
受賞したコンテストでの研究内容は生物分野ではありませんでした。出願要件を満たしますか?
出願要件ではコンテストに参加した際の研究内容を生物分野に限定していません。審査において研究内容が生物分野でなかったことを区別しませんので、7月に公表される各種出願書類を確認して出願してください。
受賞したコンテストが出願要件に記載されていないものでした。出願できますか?どのような書類が必要で、どのように記載されていないコンテストや賞を説明したら良いですか ?
出願要件の「上記以外の優れた自由研究や課題研究」に該当しますので、記載がないものでも出願できます。出願書類の「出願要件を確認する書類」の中に、H)に該当する場合に提出する「優れた自由研究や課題研究の証明書」があります。そこにはコンクール名や賞を記述する欄があり、コンテストの主催者もしくは在籍する高校の学校長などの公的立場の人物に依頼して書いてもらってください。
また出願書類の「研究報告書」にも、コンテストや賞の詳細が分かるように記載するところがあります。こちらは出願者自身が記入してください。(2025年6月4日更新)
研究を指導したのが親なのですが、親は「公的な立場」として扱われますか?親が公的な立場と扱われない場合は、志願者評価書は誰に書いてもらうべきでしょうか?
親が公的機関での教育者や研究者ではない場合は、その研究内容を理解できる公的な立場の人物(例えば、高校の学校長、担任、理科教員)に研究内容と受けた指導について具体的に説明した上で、志願者評価書の記載を依頼してください。その志願者評価書の中で、実際に指導したのが親であること、その指導がどのようなものであったのか、説明も明記してください。
高校3年目から科学コンテストに参加しても大丈夫ですか?
願書応募締め切りまでに条件を満たす必要な書類がすべて届けば大丈夫です。
出願要件では、研究プログラムやコンテスト等で入賞あるいは上位の成績を修めたなどの活動実績について求められていますが、いつ行った研究が対象になるでしょうか?
高校在籍中に、自ら行った科学分野の研究を対象とします。
令和6年度中に高校を卒業して令和7年度現在、浪人中です。「志願評価書」の作成は誰に依頼すれば良いでしょうか?
研究を実際に指導した方(高校の担任等)に書いてもらってください。
研究コンテストにグループで参加したのですが、個人の参加者よりも評価が低くなるのでしょうか?
グループで参加したという事実だけで個人の参加者よりも評価が低くなることはありません。グループで参加した場合であっても、受験者がそのグループの中で主体的に研究に取り組み、成果に貢献したのであれば、個人の参加者よりも高く評価されることもあります。研究報告書と志願者評価書に受験者本人の貢献を詳しく記載してください。
二次選考には講義に基づく小論文とあります。講義を理解するには大学レベルの生物学の知識が必要でしょうか?
いいえ。二次選考で実施される講義は高校生物で学ぶ生物の知識で理解できるように組み立ててあります。
高校での研究を大学でも続けたいのですが指導を受けることは可能でしょうか?
生命理学科には20を超える研究室が所属し、広範な生物学を網羅しています。専門の近い研究分野の研究室があれば、研究室の責任者と相談した上、高校での研究やそれに近いテーマの研究を研究室に所属して指導を受けることは可能です。
研究室の都合により指導をお引き受けできない場合があります。
この制度で生物学科を志望して入学しても生物学以外も学べるのでしょうか?
上記「総合型選抜で入学することによるインセンティブ」に記されているように、本制度で入学した学生には1年生の時点から生物学を深めるチャンスが多く用意されています。一方で、後世に残る活躍や生物学研究は、生物学の垣根を超えた発想から生まれることも多く、そのためには幅広い視野と知識の醸成が重要になります。本制度で入学した場合でも、一般入試などで入学する理学部の学生と同様に、2年生進学時の生物学科への配属までの間に生物学以外の幅広い学問分野の講義を受講することができます。
複数のコンテストに応募して受賞しています。すべてを記した方が良いのでしょうか?
自分自身として最もアピールしたい研究(受賞)を1つ選んで記載してしてく ださい。その他の研究内容は任意提出書類で提出いただいても構いません。
令和8年度向けの出願情報はいつ公表されるのでしょうか?
令和7年6月上旬に概要をこのWEBページで公表し、7月上旬に詳細(募集要項)を公表します。(2025年5月30日更新)
2025年度の総合選抜型入試についての説明会の開催予定はありますか?
今年度は8月27日17時からオンライン説明会をおこないます。事前登録が必要ですので、下のURLリンクから登録をお願いします。また、オンライン説明会の録画を後日に、この総合型選抜入試の特設HPにて公開します。それまでは、現在公開されている2024年度の説明会の動画を参考にしてください。
https://events.teams.microsoft.com/event/31bb1dc7-b5ad-469b-9845-83cdb4127265@7f54b283-22ed-4a3c-a944-75f755e58306
(2025年6月20日更新)