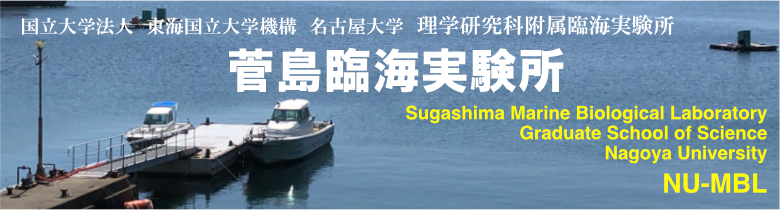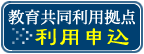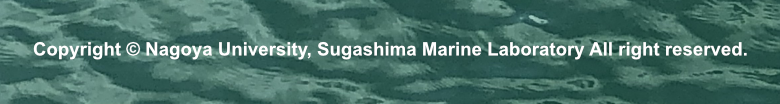研究業績
>Recent Publications (2026.01-present) >2025 >2024 >2023 >2022 >2021Recent Publications (2026.01-present)
3. Hookabe N, Shimooka S, Moritaki T, Jimi N.A New Panther Worm Spotted in Japan, Hofstenia sugashimaensis sp. nov. (Xenacoelomorpha: Acoela)
Species Diversity. >>Link
菅島臨海実験所の水槽と鳥羽水族館の水槽から得られた無腸類を新種 スガシマヒョウモンウズムシ Hofstenia sugashimaensis として記載した。屋外水槽に生えているハネモ類の緑藻に沢山絡みついている。
2. Carrerette O, Bergamo G, Shimabukuro M, Jimi N, Fujiwara Y, Sumida PYG.
Hitchhiking in the Deep: A New Amphisamytha Species (Annelida: Ampharetidae) Riding on Widespread Squat Lobster at Hydrothermal Vents in the Okinawa Trough (NW Pacific).
Deep-Sea Research Part I : Oceanographic Research Papers . >>Link
ゴエモンコシオリエビは熱水噴出域にのみ見られる特殊なコシオリエビであるが、ゴエモンコシオリエビの腕の部分をよく見るとゴカイがくっついている。これを新種 Amphisamytha goemoncola として記載した。本種はゴエモンコシオリエビからしか見つからず、共生性であると考えられる。
1.Kurita G, Adachi KA, Uesaka K, Goshima G.
Genetic switch between unicellularity and multicellularity in marine yeasts.
Nature. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
海洋由来真菌を用いた実験系を確立し、これらの真菌における多細胞-単細胞の切り替えを制御する細胞内分子メカニズムを解明した論文。生物の多細胞性の進化についての知見が深まることが期待される。
2025
22. Fourreau CJL, Jimi N, Goto R, Reimer JD.A literature review of the marine annelids of the Ryukyu Islands: still at the “early-bird” stage.
Marine Biodiversity. >>Link
琉球諸島における海産の環形動物に関する研究をレビューし、本地域における多様性の高さを明らかにした。その一方でこれまで調査されている島や環境には偏りがあることも判明し、今後の調査において空白地帯の研究を進めることで生物多様性の理解が進むと考えられる。
21. Salazar-Vallejo S, Jimi N.
Revision of Pareurythoe Gustafson (Annelida: Amphinomidae).
Journal of Natural History. >>Link
ウミケムシ科Pareurythoe属のリビジョンを行った。1930年に記載されて以来情報が少なかった ニホンウミケムシ Pareurythoe japonica についても再記載を行い、菅島の標本に基づきネオタイプを指定した。
20. Teramura A, Hookabe H, Kimura T, Jimi N, Shiraki S, Fujiwara Y.
First record of deep-water batfish THalicmetus niger Ho et al. 2008 (Lophiiformes: Ogcocephalidae) from the Kumanonada Sea with dietary analysis based on DNA metabarcoding of gut contens.
Thalassas. >>Link
クスミアカフウリュウウオを熊野灘から初報告すると共に食性をメタバーコーディングによって解析した。ナナテイソメ科の多毛類がよく食べられているようであり、深海魚による多毛類の摂餌に新たな知見を示した。
19. Ogawa HA, Ochiai KK, Shirae-Kurabayashi M, Goshima G.
RNAi reveals a unique set of kinesins mediating chloroplast motility in the giant cytoplasm of Bryopsis (Ulvophyceae), a coenocytic green alga.
Journal of Phycology. >>Link
巨大単細胞緑藻ハネモ(Bryopsis sp.)において、RNAi法を適用する2つの手法を開発した。また全34種のキネシン遺伝子の網羅的な解析の結果、葉緑体の逆行性・順行性輸送に関与するキネシン5種を同定した。
18. Jimi N, Pratama GA, Ogawa A, Fujiwara F, Hookabe N.
Two new deep-sea myzostomid species (Annelida: Myzostomida) from the Northwest Pacific off Japan.
Plankton and Benthos Research. >>Link
しんかい6500に乗って得られたウミシダからPulvinomyzostomum unicorne ユビツキスイクチムシを、ツノサンゴからEenymeenymyzostoma abyssale ゴシンボクスイクチムシを新種として記載した。刺胞動物に共生する例は非常に稀であり、まだ未知の多様性がスイクチムシには広がっていると考えられる。
17. Chen C, Watanabe HK, Hookabe N, Shiraki S, Nye V, Fleming JF, Jimi N.
Biological surveys reveal unexpectedly high faunal diversity at Nankai Trough methane seeps.
Ecosphere. >>Link
日本の5つの湧水域に関して統合的な調査を行ったところ、非常に多様で特有な生物相であることが明らかになった。メタンハイドレート開発への関心が高まる中で各地域固有の保全対策を行う必要性を示した。
16. Oya Y, Hookabe N, Jimi N, Furushima Y, Fujiwara Y.
Description of a new bathyal species of Notocomplana (Platyhelminthes, Polycladida) collected from Bathymodiolus aggregations in a deep-sea hydrocarbon seep
Zootaxa. >>Link
湧水域からヒラムシの新種を記載した。深海におけるヒラムシ類の多様性はほとんど明らかになっていないが、普段浅海からよく見つかるNotocomplana属が湧水域に密集して生息していることは驚きの生態である。
15. Yamashita R, Anai R, Sato H, Shimooka S, Ogawa H, Kon K.
Structure of the interstitial macrobenthic community in the intertidal pebble beach of Japan.
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. >>Link
静岡県に広がる中礫浜の間隙環境に生息するマクロベントスの生物相をまとめるとともに、環境要因との関係や季節変動について調べた。礫浜はこれまであまり注目されてこなかった環境だが、生物多様性及び生態系の観点から重要である。
14. Jimi N, Manzano GG, Hookabe N, Kise H, Reimer JD, Woo SP, Fujiwara Y.
New deep sea terebellid polychaete with sucker like ventral pads adapted to a sediment free environment.
Scientific Reports. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
フサゴカイ科も基本的には堆積物に埋没して生活するが、南大東島において見つかった新種キュウバンフサゴカイは樹上性のカイメンに付着して生活する生態を送っていた。また、同属他種には見られない吸盤状の形質を獲得しており、堆積物がない環境への進出に寄与していると考えられる。
13. Bessho-Uehara M, Jimi N, Fujiwara Y.
A bioluminescent deep-sea polychaete within the genus Aricidea (Paraonidae) from Minamidaito Island, Japan.
Scientific Reports. >>Link
多毛類は発光するグループが多系統的に知られており、化学的にも興味深い分類群である。本研究では南大東島沖の深海からヒメエラゴカイ科が発光することを初めて発見した。
12. Ochiai KK, Toyoda A, Itoh T, Goshima G, Uesaka K.
High-quality metagenome-assembled genomes of bacteria associated with long-term cultivated giant coenocytic green alga Bryopsis.
Microbiology Resource and Announcements. >>Link
海藻に付着する細菌の全体像を知ることは、その海藻の成長に関わる共生細菌を明らかにする上で重要である。本研究では研究室で培養している大型緑藻ハネモのメタゲノム解析により、ハネモに付着・内在する50の高精度な細菌メタゲノムアセンブリゲノム (MAGs) を決定した。そのうち44 MAGsは新規の種である可能性が高く、 ハネモ-細菌間の多様な関係性が示唆された。
11. Jimi N, Hookabe N, Woo SP, Kohtsuka H.
Two new genera and species of Polynoidae (Annelida: Polychaeta) associated with sea urchins.
Zoological Studies. >>Link
ウニ類は毒のある棘を備え共生相手として優れた宿主であるのにもかかわらず、他棘皮動物に比べて多毛類の宿主として知られている例は限られている。オーストンフクロウニおよびヤマタカタコノマクラからウロコムシを採集し、2新属2新種として記載した。また、棘皮動物共生性ウロコムシの進化は棘皮動物の大系統と一致していることを明らかにした。
10. Hookabe N, Yamamori L, Ogawa A, Jimi N, Kohtsuka H, Rouse GW.
An updated phylogeny of Iphitime (Annelida: Dorvilleidae) revealing multiple host switching, with description of I. nubila sp. nov. .
Zoological Journal of the Linnean Society. >>Link
コイソメ類の中で突然共生性になったミノイソメ Iphitime属の系統関係を明らかにし、ヤドカリの殻の中から新種ウンリュウミノイソメ Iphitime nubilaを記載、タカアシガニの鰓からミノイソメの再記載を行った。
9. 小西 晶子・佐藤 大義・自見 直人.
三重県鳥羽市菅島から採集されたツメナシピンノ (甲殻亜門カクレガニ科)の記録.
名古屋大学博物館報告.>>Link
菅島臨海実験所の公開臨海実習「海産無脊椎動物の多様性」において、実験所前の海でウミギク属の一種と共生する稀種ツメナシピンノを採集した。本種のホロタイプは失われており、原記載である1939年以降タイプ産地である伊勢湾から標本を伴った記録がないため、詳細な観察を行い報告した。 ポストコースリサーチ制度を利用して実習生であった第一著者が実験所に再来し取り組んだ研究である。
8. Hookabe N, Manzano GG, Jimi N, Kise K, Reimer JD, Tsuchida S, Fujiwara Y.
Ribbon worms living on deep-sea trees: Alvinonemertes daitoensis sp. nov. (Nemertea, Monostilifera) associated with the glass sponge Walteria leuckarti (Porifera, Hexactinellida).
Systematics and Biodiversity. >>Link
海山に生える樹状のガラス海綿の表面に共生するヒモムシを記載した。八放サンゴやハオリムシ等起立性の生物に共生する変なヒモムシであり、海綿からは初の報告となる。
7. Ochiai KK, Goshima G.
Ruegeria strains promote growth and morphogenesis of the giant coenocytic alga Bryopsis.
The Journal of Experimental Botanity. >>Link
海藻には多くの細菌が付着しているが、それらが海藻にどういった影響を与えているかはほとんどわかっていない。本研究では、Ruegeria属の細菌が、巨大単細胞性海藻ハネモの成長や形態形成を促進することを見出した。
6. Shimooka S, Koyama A, Jimi N.
A New Species of Linopherus (Annelida: Amphinomidae) from Kyushu, Japan.
Species Diversity. >>Link
瀬戸内海からウミケムシ科の新種 Linopherus littoralis ハマドロウミケムシを記載した. Linopherus属を含めた分子系統解析を初めて行ったが、正しい系統的位置については今後の検証が必要.
5. Springer C, Sato SD, Oguchi K, Jimi N, Miura T, Aguado MT.
Two new species of Syllidae (Annelida) from Misaki Bay and Sugashima Island, Japan.
Zootaxa. >>Link
三崎臨海と菅島臨海からシリス科の2新種を記載し、それぞれの系統的な位置を決定した.Virchowia属の系統的な位置については今後の検証が必要である.
4. Kodama M, Mukaida Y, Hosoki TK, Jimi N.
A new species of the genus Lepechinella Stebbing, 1908 (Crustacea: Amphipoda: Lepechinellidae) from Japan.
Zootaxa.>>Link
屋久島沖から新種トゲナガガイコツヨコエビを記載した.
3. Tsuyuki A, Shimooka S, Oya Y. Record of Euilyoida takewakii (Kato, 1935) (Platyhelminthes, Polycladida, Acotylea) from Fukuoka, Japan, with notes on its phylogenetic position.
Plankton and Benthos Research. >>Link
ニホンクモヒトデの盤の内部に寄生する珍しいクモヒトデヒラムシを福岡県から記録し、系統的位置を報告した.
2. Jimi N, Hookabe N, Woo SP, Fujiwarab Y. Taxonomy and ecological insights into Melinnopsis shinkaiae sp. nov., a polychaete with a vertical tube from the Daiichi-Kashima seamount (Northwest Pacific).
Plankton and Bethos Research.>>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
しんかい6500に乗って窓から見つけたゴカイをタケウマカザリゴカイとして記載した.また、垂直に立ち上がる巣の先端で暮らす生態について報告した.
1. Nishi E, Abe H, Jimi N, Tanaka K, Kobayashi G, Makiguchi N, Kupriyanova EK.
Description of a Reef-forming Neosabellaria upopoy sp. nov. (Annelida: Polychaeta: Sabellariidae) from Shallow Waters off Iburi, Hokkaido, Japan, with Notes on its Reproduction and Early Development.
Sessile Organisms.>>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
北海道白老町沖に設置されたタンデム型人工リーフに巨大な礁を形成しているカンムリゴカイの新種記載.人工リーフが漁場や水産資源に与える影響をモニタリングしている中で発見された.
2024年
24. Ohashi A, Fukuoka M, Kanzaki T, Hirose M, Takada K, Ise Y.Unveiling the predator–prey interaction between a newly discovered nudibranch and sponge with molecular evidence.
Fisheries Science. >>Link
菅島近海で発見された海綿動物Phorbas sugashimaensis sp. nov. とその海綿動物に付着して見つかるウミウシ Rostanga confitura sp. nov.の2種を新種記載し、ウミウシと海綿動物における捕食者と被食者の相互作用を明らかにした.
23. 木村妙子・木村昭一・藤本心太・櫛田優花・露木葵唯・波々伯部夏美・下岡敏士・自見直人・白木祥貴・中島広喜・小川晟人・鄧宗靖・幸塚久典・喜瀬浩輝・角井敬知・松下拓輝・Gregorius Altius Pratama・小林格・胡品燚・前川陽一・中村亨・奥村順哉・高野雅貴.
熊野灘の深海底生動物相〜2023年勢水丸研究航海から.
三重大学大学院生物資源学研究科紀要 >>Link
2023年に行われた勢水丸の研究航海で得られた標本を元に熊野灘の深海底生動物相を明らかにした. 16地点、水深101〜802mの範囲で調査を行い、12動物門を得た.
22. Nishi E, Tanaka K, Jimi N, Tovar-Hernández MA.
A new species of Euchonoides (Annelida, Polychaeta, Sabellidae) from Suruga Bay, Japan.
Plankton and Bethos Research. >>Link
駿河湾からケヤリムシの新種 Euchonoides shizuoka フタマキケヤリムシを記載した。微小なケヤリムシは大型のものに比べ見つかりづらくあまり研究が進んでいない。
21. Chen C, Hookabe N, Hashimoto R, Shimooka S, Shiraki S, Uyeno D, Kawagucci S.
Faunal Composition of the Sumisu Caldera Hydrothermal Vent Field as a Key Baseline for Conservation in Light of Deep-Sea Mining.
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. >>Link
JAMSTECよこすか・しんかい6500による研究航海で伊豆小笠原弧にある須美寿カルデラ熱水域の生物相調査を26年ぶりに行った。記録された動物種多様性は9種から54種に大きく更新された。
20. Jimi N, Hookabe N, Shiraki S, Yokooka H, Woo SP, Tsuchida S, Fujiwara Y.
A new species of Flabelligena (Acrocirridae: Annelida) from the Western Pacific.
Species Diversity. >>Link
間隙性のクマノアシツキの新種。南大東島および北高鵬海山の斜面にある砂をROVで吸う必要があり、ドレッジ等通常の手段では採集が難しいことから採れていなかったと思われる。海山の生物多様性はまだまだこれから。
19. 福岡雅史
海藻類、棘皮動物類のモニタリング調査について
臨海・臨湖 No. 41(国立大学法人 臨海・臨湖実験所・センター 技術職員研修会議会誌)>>>Link
2021~24年にかけて実施した実験所前の磯場における海藻類の変動と藻場消失(磯焼け)の要因の一つとされるウニ類を含む棘皮動物類の個体数変動をモニタリング調査した結果を報告した。
18. Jimi N, Hookabe N, Imura S, Diez YL.
Two new species of Schizorhynchia (Kalyptorhynchia: Rhabdocoela: Platyhelminthes) from Japan.
Zoosystematics and Evolution. >>Link
砂の隙間に住む扁形動物隠吻類の2新種記載。間隙性の柔らかい生き物たちは日本においてほとんど研究が進んでおらず、まだまだこれから多様性を明らかにしていく必要がある分類群。
17. Goda M, Shribak M, Ikeda Z, Okada N, Tani T, Goshima G, Oldenbourg R, Kimura A.
Live-cell imaging under centrifugation characterized the cellular force for nuclear centration in the Caenorhabditis elegans embryo.
Proc Natl Acad Sci USA. >>Link
米国ウッズホール臨海実験所(MBL)での共同研究成果。細胞内で核が移動するときにどれくらいの力がかかっているかが突き止められた。MBLにしかない顕微鏡を駆使した、MBLらしい国際共同研究。顕微鏡を開発された井上信也博士は2019年に逝去され、その顕微鏡は日本の遺伝研に移設された。日本でもこんな共同研究がしてみたい。
16. Koyama A, Imai T, Matsushima K, Shimooka S.
Sub-habitat classification of temperate salt marshes in Japan based on aquatic fauna.
Global Ecology and Conservation. >>Link
福岡県の汽水域の塩性湿地101地点を動物相から6つに類型化した。これらの生物多様性の異なる生息地を保全していくことが重要。
15. Jimi N.
The Polychaetous Annelids of Japan: Updated Checklist of Known Species.
Species Diversity. >>Link
日本産の多毛類のリストを1700年代から今までの650以上の文献に基づき整理した。これまで日本からは1194種知られていたが実際には1683種がこれまで報告されており、約500種は見逃されていたことがわかった。
14. Tago T, Fujii S, Sasaki S, Shirae-Kurabayashi M, Sakamoto N, Yamamoto T, Maeda M, Ueki T, Satoh T, Satoh AK.
Cell-wide arrangement of Golgi/RE units depends on the microtubule organization.
Cell Struct Funct. >>Link
いくつかの動物種におけるゴルジ体/小胞体ユニットの細胞内動態について解析を行い、その集合や散在の制御が微小管モーターに依存していることを明らかにした。
13. Jimi N, Fujiwara Y, Kajihara H.
Evaluation of “Cirriformia tentaculata” (Annelida: Cirratulidae) from Japan as a Pollution Indicator in Marine Environments: Is it Truly a Single Species?
Species Diversity.>>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
日本産ミズヒキゴカイはCirriformia tentaculataとされ有機汚濁の環境指標としても用いられてきたが、日本1周し全国的にサンプルを集めて再検討を行った結果12種に分かれることがわかった。また、それぞれの生息環境は異なっており、“ミズヒキゴカイ“を環境指標として用いることは適切ではないことを示した。
12. Yamasaki H, Yoshida M, Jimi N, Hookabe N, Sako M, Kohtsuka H, Fujimoto S.
Kinorhynch fauna from Oki Islands, with the description of a new Echinoderes species and its phylogenetic relationships within the family Echinoderidae.
Zoologischer Anzeiger. >>Link
隠岐臨海実験所周辺で採集された動吻動物の新種記載とEchinoderidaeの分子系統解析を行った。
11. Hookabe N, Jimi N, Furushima Y, Fujiwara Y.
Discovery of deep-sea acoels from a chemosynthesis-based ecosystem.
Biology Letters.>>Link
無腸類は珍無腸動物門に属する無脊椎動物であり、主に浅海域から知られるがその生態はよく分かっていない。相模湾初島沖にある湧水域から新属新種の無腸類 ハツシマシアワセウズムシを記載した。本種は化学合成生態系から記載された初めての無腸類であり、珍無腸動物門で少なくとも2回化学合成生態系への進出があったことを示唆している。
10. Jimi N, Britayev T, Sako M, Woo SP, Martin D.
A new genus and species of nudibranch-mimicking Syllidae (Annelida, Polychaeta).
Scientific Reports. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
>>文教速報デジタル版
>>沖縄タイムズ+プラス
>>NHK NEWS WEB
>>中日新聞
ウミトサカに共生する新属新種のケショウシリスは刺胞毒をもつウミウシにそっくりの形や色彩をしていることから、ベイツ型もしくはミュラー型擬態であると考えられる。環形動物では非常に珍しい例であり、剛毛を疣足の中に隠しているという変わった形質もゴカイらしさを消している。本属においてこれらの形質は獲得されており、擬態がどのように進化するかの研究材料として格好の対象である。
9. Hookabe N, Jimi N, Fujimoto S, Kajihara H.
Revisiting Stygocapitella (Annelida, Parergodrilidae) in Japan, with insights into their amphi-Pacific diversification.
Royal Society Open Science. >>Link
多毛類は基本的に海に生息するが、一部は陸上に生息する。Stygocapitella属は海岸の潮上帯よりも更に上の海水が被ることのない砂の中に住んでいる変わったゴカイだが、実は日本にも分布している。本研究は2種を報告しそのうち1種を新種として記載した。
8. Hookabe N, Jimi N, Ogawa A, Tsuchiya M, Sluys R.
The abyssal parasitic flatworm Fecampia cf. abyssicola: new records, anatomy, and molecular phylogeny, with a discussion on its systematic position.
Biological Bulletin. >>Link
寄生性の扁形動物であるFecampia cf. abyssicolaを深海から報告し、筋肉および神経系の形態観察・分子系統解析を行い系統的位置について議論した。
7. Ochiai KK, Hanawa D, Ogawa HA, Tanaka H, Uesaka K, Edzuka T, Shirae-Kurabayashi M, Toyoda A, Itoh T, Goshima G.
Genome sequence and cell biological toolbox of the highly regenerative, coenocytic green feather alga Bryopsis.
The Plant Journal. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
>>Science Japan(JST) 英語
>>客観日本(JST) 中国語
菅島近海で採取された巨大単細胞緑藻ハネモ (Bryopsis sp.) の全ゲノムを高精度に解読した。本研究により、ハネモのみならず、高精度のゲノム情報の少ない大型藻類における実験生物学の発展が期待される。
6. 木村妙子・木村昭一・自見直人・喜瀬浩輝・波々伯部夏美・藤本心太・中島広喜・松尾拓己・山崎博史・小林格・小川晟人・櫛田優花・前川陽一・中村亨・奥村順哉・高野雅貴
伊勢湾南部潮下帯の底生動物相.
三重大学フィールド研究・技術年報. >>Link
伊勢湾南部海域潮下帯の底生動物を三重大学の調査船勢水丸で徹底的に調査した論文。
5. Hasegawa N, Hookabe N, Fujiwara Y, Jimi N, Kajihara H.
Supplemental re-description of a deep-sea ascidian, Fimbrora calsubia (Ascidiacea, Enterogona), with an inference of its phylogenetic position.
Zoosystematics and Evolution. >>Link
肉食性のホヤを宝永海山から採集し、その系統的位置を推定した。肉食はホヤ類の中で少なくとも3回獲得されたことが明らかになった。
4. Nishi E, Tomioka S, Jimi N, Fujiwara Y, Kupriyanova EK.
A new species of Amphictene (Annelida, Polychaeta, Pectinariidae) from off Kushiro, Hokkaido, Japan.
Plankton and Benthos Research. >>Link
釧路沖の深海からウミイサゴムシ科の1新種を記載した。
3. Komori S, Yamabe S, Matsuta R, Yamazaki Y, Fukuoka M, Sato S, Takada K.
Mebamamide C, a deoxy analogue of mebamamides in Bryopsis marine green algae and Elysia sacoglossan mollusks.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. >>Link
藻類Bryopsis sp.(ハネモ属)から新しい環状デプシペプチドMebamamide Cの単離と構造決定をし、Bryopsis(藻類)と捕食者であるElysia(軟体動物)間での化学的関係、共生関係を調査した。
2. Nakajima H, Sato T, Jimi N.
Superfamily Eurysquilloidea (Crustacea: Stomatopoda) from Japan.
Species Diversity. >>Link
日本から未発見だった上科、Eurysquilloideaに属するManningia andamanensis ヘコミマニングシャコを沖縄から報告した。
1. Jimi N, Hookabe N, Fujimoto S, Kise H, Ogawa A, Tsuchiya M.
Three species of Fauveliopsidae (Annelida) from the northwestern Pacific including a new species.
Plankton and Benthos Research. >>Link
深海に生息するイモムシゴカイ科の3種を日本から報告し、そのうち1種を新種として記載した。
2023年
16. Jimi N, Nakajima H, Sato T, Gonzalez BC, Woo SP, Rouse GW, Britayev TA.Two new species of Parahesione (Annelida: Hesionidae) associated with ghost shrimps (Crustacea: Decapoda) and their phylogenetic relationships.
Peer J. >>Link
Parahesione属は特異的な形をもつオトヒメゴカイとして知られるが、1880年の記載以来ほとんど記録がなく謎の分類群であった。沖縄、パプアニューギニア、ベトナムのスナモグリの巣穴から採集された標本に基づき2新種を記載し、巣穴共生に適応していると考えられる形質について議論した。
15. Yamazaki Y, Yamabe S, Komori S, Yoshitake K, Fukuoka M, Sato S, and Takada T.
Structure Determination of Kahalalide Analogues Based on Metagenomic Analysis of a Bryopsis sp. Marine Green Alga.
Journal of Natural Products. >>Link
Elysia rufescens(クシモトミドリガイ)から単離された海洋天然化合物のKahalalideはがん細胞への活性が見られる有用な化合物である。このKahalalideの起源は緑藻のハネモ属に共生する細胞内細菌であることが明らかになっている。 私たちは実験所周辺からハネモ属とそれを食しているElysia属のウミウシを採集し、Kahalalideと捕食者の化学的関係を明らかにする研究を行った。その過程でハネモ属から新たに2種類のKahalalideを発見した。
14. Yoshida MW, Oguri N, Goshima G.
Physcomitrium patens SUN2 mediates MTOC association to the nuclear envelope and facilitates chromosome alignment during spindle assembly.
Plant Cell Physiol. >>Link
中心体のない植物細胞の分裂に必要な微小管構造を配置する仕組みの一端を突き止めた。ヒメツリガネゴケの核膜タンパク質SUN2の欠失により、核膜と微小管形成中心(MTOC)との相互作用が弱まった。細胞分裂進行の遅延も認められた。
13. Sato M, Jimi N, Itani G, Henmi Y, Kobayashi S.
Synonymy of the scale worm Hesperonoe urechis with Arctonoella sinagawaensis (Annelida: Polynoidae), newly recorded from the Seto Inland Sea, Western Japan, with remarks on symbiosis with the spoon worm Urechis unicinctus (Annelida: Thalassematidae).
Species Diversity. >>Link
ユムシに共生するシナガワウロコムシ Arctonoella sinagawaensis (Izuka, 1912) を近年採集した標本に基づき再記載し、Hesperonoe urechis Marin and Antokhina, 2020 は本種の新参異名であることを形態および分子情報に基づき示した。
12. Kayama-Watanabe H, Uyeno D, Yamamori L, Jimi N, Chen C.
From commensalism to parasitism within a genus-level clade of barnacles.
Biology Letters. >>Link
コガネウロコムシ類の体に根を張るようにして寄生する変なフジツボの系統的位置を決定し、通常の固着性のフジツボから寄生性への進化過程を明らかにした。
11. Sawada H, Inoue S, Saito T, Otsuka K, Shirae-Kurabayashi M.
Involvement in Fertilization and Expression of Gamete Ubiquitin-Activating Enzymes UBA1 and UBA6 in the Ascidian Halocynthia roretzi.
International Journal of Molecular Sciences. >>Link
尾索動物マボヤの受精には細胞外のユビキチン-プロテアソーム系が関与していると考えられる。本研究ではマボヤの受精がユビキチン活性化酵素(UBA/E1)の阻害剤PYR-41によって強く阻害されることを示した。そこでマボヤユビキチン活性化酵素UBA1, UBA6を同定しAlphaFold2によりその立体構造を推定した。これらは哺乳類のUBA1, UBA6との類似性を示した。 さらにマボヤUBA1, UBA6の抗体を作成し局在解析を行ったところ精子のミトコンドリア周辺に局在したことから、受精の際にこれらのユビキチン活性化酵素が卵膜構成因子VC70を分解する可能性が示唆された。
10. Hookabe N, Fujino Y, Jimi N, Ueshima R.
At the edge of the sea: the supralittoral nemertean, Acteonemertes orientalis sp. nov. (Nemertea: Eumonostilifera: Plectonemertidae) from Japan.
Invertebrate Systematics. >>Link
通常は海中に生息する紐形動物だが、極一部のグループが陸上に生息する。Acteonemertes属のヒモムシは1種しか知られていなかったが、日本の海岸の波がかからない陸域に生息しているものを発見し新種として記載した。属の判別形質を本研究で得られた成果に従って修正した。
9. Jimi N, Shinji J, Hookabe N, Okanishi M, Woo SP, Nakano T.
A new species of Branchellion (Hirudinea: Piscicolidae) parasizitzing the gills of short-tail singrays (Batoidea: Dasyatidae) from the West Pacific.
Zoological Science. >>Link
ホシエイに寄生するヒルの新種記載。水族館等で飼われているホシエイに寄生するヒルは正体がよくわかっていなかったが、本研究で明らかになった。オーストラリアやマレーシアから記録されていたBranchellion属の不明種も本種であることを明らかにし、 西太平洋に広域な分布を持つことが判明した。
8. Tsuyuki A, Oya Y, Jimi N, Hookabe N, Fujimoto S, Kajihara H.
Theama japonica sp. nov., an Interstitial Polyclad Flatworm Showing a Wide Distribution along Japanese Coasts.
Zoological Science. >>Link
間隙性のヒラムシの新種記載。ヒラムシの仲間は基本的には大型で岩の裏等に生息するが、本属は砂の隙間に住む非常に微小なグループ。ハプロタイプネットワークを構築し、本種の分散能についても議論した。
7. Yoshida MW, Hakozaki M, Goshima G.
Armadillo repeat-containing kinesin represents the versatile plus-end-directed transporter in Physcomitrella.
Nat Plants. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
ARKと呼ばれるモータータンパク質がコケ植物細胞内で幅広く物質輸送を担うことを発見した。動物では40年近く前から「運び屋」の正体はわかっていたが、植物では見つかっていなかった。ヒメツリガネゴケを実験材料として用いて、ようやく突き止めた。
6. Kurita G, Goshima G, Uesaka K.
Draft Genome Sequences of Two Dothideomycetes Strains, NU30 and NU200, Derived from the Marine Environment around Sugashima, Japan.
Microbiol Resour Announc. >>Link
菅島臨海における海生真菌生物学研究の第二報。菅島で採取され興味深い表現型を示す黒色酵母NU30株とNU200株の全ゲノム配列を決定した。菅島臨海学生と本学のバイオインフォマティシャンの共同研究。
5. Jimi N, Kobayashi I, Moritaki T, Woo SP, Tsuchida S, Fujiwara Y.
Insights into the diversification of deep-sea endoparasites: Phylogenetic relationships within Dendrogaster (Crustacea: Ascothoracida) and a new species description from a western Pacific seamount.
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. >>Link
寄生性のフジツボであるシダムシはヒトデの中で生活しているが、属内の系統関係はよくわかっていなかった。本研究では安永海山から得られたミズカキヒトデに寄生するシダムシを新種として記載し、初めて属内の分子系統解析を行うことで深海の内部寄生性生物の種分化過程を考察した。
4. Jimi N, Bessho-Uehara M, Nakamura K, Sakata M, Hayashi T, Kanie S, Mitani Y, Ohmiya Y, Tsuyuki A, Ota Y, Woo SP, Ogoh K.
Investigating the diversity of bioluminescent marine worm Polycirrus (Annelida), with description of three new species from the Western Pacific.
Royal Society Open Science. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
>>ライブドアニュース
>>中日新聞
青紫色に発光するPolycirrus属の3新種の記載と発光生態の観察。3新種全て発光することを現場および実験室において確認した。種分類と発光生態の情報を結びつけることで、今後の発光生物学の発展の基盤となる。
3. Jimi N, Fujita T, Woo SP.
Four new species of coral- and rock-boring polychaetes Daylithos (Annelida, Flabelligeridae) from the Pacific Ocean.
Zoosystematics and Evolution. >>Link
サンゴや岩に穿孔して生活するハボウキゴカイDaylithos属を日本各地の標本を元に見直し、日本から3新種、マレーシアから1新種記載した。アクアリウム用のサンゴと共に海外から意図せず輸入されており、日本の多様性を把握することで外来種の蔓延を防ぐ基盤となる。
2. Ta KN*, Yoshida MW*, Tezuka T, Shimizu-Sato S, Nosaka-Takahashi M, Toyoda A, Suzuki T, Goshima G, Sato Y.
Control of plant cell growth and proliferation by MO25A, a conserved major component of the Mammalian Sterile20-like kinase pathway.
Plant and Cell Physiology. >>Link
* equal contribution
シグナル伝達関連因子MO25Aが植物細胞の成長や増殖に重要であることをヒメツリガネゴケとイネを使って示した共同研究。
1. Cejp B, Jimi N, Aguado MT.
Another piece for the syllid puzzle: A new species from Japan and its mitochondrial genome reveal the enigmatic Clavisyllis (Phyllodocida: Syllidae) as a member of Eusyllinae.
Zootaxa. >>Link
世界から2種しか知られておらずどこに属するか謎に包まれていたClavisyllis属のミトコンドリアDNA全長配列決定をおこない系統的位置を推定した。また形態観察に基づき日本から初めて本属の新種を記載した。
2022年
22. 自見直人.イッスンボウシウロコムシ──矮雄を背負う変なゴカイ. 京都大学フィールド科学教育研究センター (編) 海産無脊椎動物多様性学 100年の歴史とフロンティア. 京都大学学術出版会. 706 pp.
Japanese only.
21. Hookabe N, Moritaki T, Jimi N, Ueshima R.
A new oerstediid discovered from wood falls in the Sea of Kumano, Japan: Description of Rhombonemertes rublinea gen. et sp. nov. (Nemertea: Eumonostilifera).
Zoologischer Anzeiger. >>Link
熊野灘の沈木から見つかったヒモムシに基づき新属新種 Rhombonemertes rublinea gen. et sp. nov.を記載した。
20. Taylor A, Mortimer K, Jimi N.
Unearthing the diversity of Japanese Magelona (Annelida: Magelonidae); three species new to science, and a redescription of Magelona japonica.
Zootaxa 5196: 451–491. >>Link
日本産モロテゴカイ科のレビュー。日本各地の標本を網羅的に観察した結果日本におけるモロテゴカイの多様性の解像度を大きく上げた。日本から記載されていたM. japonicaをタイプ標本を元に整理した後に、3新種を記載した。
19. Shimada D, Jimi N.
Taxonomic revision of the free-living marine nematode genus Deontostoma (Enoplida: Leptosomatidae) and inclusion of a new species from the Southern Ocean.
Nematology (online first). >>Link
白鳳丸KH-19-6-Leg4航海で南極海において採集した線虫の新種を記載し、Deontostoma属のリビジョンを行った。
18. Hookabe N, Kajihara H, Chernyshev AV, Jimi N, Hasegawa N, Kohtsuka H, Okanishi M, Tani K, Fujiwara Y, Tsuchida S, Ueshima R.
Molecular phylogeny of the genus Nipponnemertes (Nemertea: Monostilifera: Cratenemertidae) and descriptions of 10 new species, with notes on small body size in a newly discovered clade.
Frontiers in Marine Science. >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
北西太平洋沿岸(日本本州~ウラジオストク)の潮間帯~深海域からニッポンネメルテス属(紐形動物門:単針類)の10新種のヒモムシを発見し、系統解析の結果ニッポンネメルテス属における体サイズの小型化は深海環境への適応である可能性が示唆された。 10新種のうち2種、Nipponnemertes crypta カクレオメンヒモムシおよび Nipponnemertes sugashimaensis スガシマスジナシヒモムシ は理学研究科附属臨海実験所を利用して三重県鳥羽市菅島近海において発見されたものである。
17.
Jimi N, Tsuchida S, Kayama Watanabe H, Ohara Y, Yokooka H, Woo SP, Fujiwara Y.
Worm on worm: two rare genera of Calamyzinae (Annelida, Chrysopetalidae), with a description of new species.
Parasitology International.
>>Link
共生性タンザクゴカイ科稀属2種の記載および系統的位置の議論。1種はCalamyzasというゴカイに寄生するゴカイであり、非常に特異な形態と生態をしているが1932年に1種報告されて以来同属他種が知られていなかった幻のゴカイ。
16.
Kin I, Jimi N, Ohtsuka S, Mizuno G, Nakamura T, Maekawa Y, Oba Y.
The COI haplotype diversity of the pelagic polychaete Tomopteris (Annelida: Tomopteridae) collected from the Pacific coast off Kii Peninsula, central Japan.
Plankton and Benthos Research.
>>Link
日本産のオヨギゴカイ科の標本の分子系統解析と形態観察を行ったところ、オヨギゴカイには想像以上の多様性があることを示しいくつかのクレードにおいて生物発光を確認した。
15.
Jimi N, Chen C, Fujiwara Y.
Two new species of Branchinotogluma (Polynoidae: Annelida) from chemosynthesis-based ecosystems in Japan.
Zootaxa.
>>Link
熱水域および湧水域からウロコムシ2新種を記載した。Branchinotogluma 属は化学合成生態系のみから知られる特殊なグループで特にB. nikkoensisの系統的な位置は寄生性の近縁属との関係を考える上でも興味深い。
14.
Nishi E, Abe H, Tanaka K, Jimi N, Kupriyanova EK.
A new species of the Spirobranchus kraussii complex, S. akitsushima (Annelida, Polychaeta, Serpulidae), from the rocky intertidal zone of Japan.
ZooKeys.
>>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
ヤッコカンザシゴカイはこれまで世界共通種とされてきたが、日本産種は別種であることがわかり新種として記載した。本種の石灰質の管は遺骸として岩礁上に数千年単位で長く残ることから、過去の平均海面の推定の際に良好な指標となり、実際に地震による土地の隆起や沈降の証拠として利用されている。
13.
Ogawa A, Jimi N, Hiruta SF, Chen C, Kobayashi I, Pratama GA, Tanaka H, Okanishi M, Komatsu H, Ikehara M.
Taxonomy and distribution of deep benthos collected in and around the Southern Ocean during the 30th Anniversary Expeditions of R/V Hakuho Maru: Annelida, Mollusca, Ostracoda, Decapoda, and Echinodermata.
Polar Science.
>>Link
南極海においてドレッジおよびマルチプルコアラーによって採集された深海底生生物とその分布をまとめた論文。
12.
Jimi N,, Hasegawa N, Taru M, Oya Y, Kohtsuka H, Tsuchida S, Fujiwara Y, Woo SP.
Five New Species of Flabelligera (Flabelligeridae: Annelida) from Japan.
Species Diversity.
>>Link
日本においてカンテンハボウキ Flabelligera affinisと呼ばれている種を全国の標本を元に見直し、分類学的な整理を行った。日本にはFlabelligera affinis は存在しないことを明らかにし、各地域の標本に基づきFlabelligera 属5新種を記載した。
11.
Kozgunova E, Yoshida MW, Reski R, Goshima G.
Spindle motility skews division site determination during asymmetric cell division in Physcomitrella.
Nat Commun.
>>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
ヒメツリガネゴケを用いた細胞観察実験により、中心体に依存しない植物細胞の分裂の際にも紡錘体がアクチン骨格依存的に動きうること、紡錘体の動きに応じて分裂面の位置が変わることを見出した。
10.
Hookabe N, Motobayashi H, Jimi N, Kajihara H, Ueshima R.
First record of the decapod-egg predator Ovicides paralithodis (Nemertea, Carcinonemertidae) from the snow crab Chionoecetes opilio (Decapoda, Brachyura).
Parasitology International.
>>Link
ズワイガニの卵巣からタラバガニヒモムシを発見した。今まではタラバガニの卵巣からしか知られていなかったが、これによりタラバガニヒモムシは多宿主性であることを示した。また、どのように多宿主性を維持できるかを議論した。
9.
Jimi N, Fujimoto S, Fujiwara Y, Oguchi K, Miura T.
Four new species of Ctenodrilus, Raphidrilus, and Raricirrus (Cirratuliformia, Annelida) in Japanese waters, with notes on their phylogenetic position.
Peer J.
>>Link
砂浜・潮間帯の岩の裏・深海の鯨骨と様々な間隙環境に生息する微小なグループの多毛類4新種記載を行い、Ctenodrilus, Raphidrilus, Raricirrus属の系統的位置について議論した。
8.
Kim J, Goshima G.
Mitotic spindle formation in the absence of Polo kinase.
Proc Natl Acad Sci U S A.
>>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
実験室内での生物進化誘導実験により、細胞分裂を制御する潜在機構を明らかにした論文。
7.
Yi P, Goshima G.
Division site determination during plant asymmetric division.
Plant Cell.
>>Link
植物細胞の非対称分裂機構について、細胞極性と核輸送の観点から論じた総説。
6.
Aguado MT, Ponz-Segrelles G, Glasby CJ, Ribeiro RP, Nakamura M, Oguchi K, Omori A, Kohtsuka H, Fisher C, Ise Y, Jimi N, Miura T.
Ramisyllis kingghidorahin. sp., a new branching annelid from Japan.
Organisms Diversity & Evolution.
>>Link
>>プレスリリース(東京大学)
佐渡島近海における潜水調査により、体が分岐する新種の環形動物を発見し、キングギドラシリスと命名した。左右相称の動物において、体幹部が分岐する体制をもつものは極めて稀である。
本種の体は尾部に向かって幾度も分岐し、宿主となるカイメンの中で縦横無尽に張りめぐらせている。進化学的にも発生学的にも非常に興味深いキングギドラシリスの発見は、左右相称動物の形態の進化過程を探る手がかりともなりうる。
5.
Hookabe N, Jimi N, Yokooka H, Tsuchida S, Fujiwara Y.
Lacydonia shohoensis (Annelida, Lacydoniidae) sp. nov. – a new lacydonid species from deep-sea sunken wood discovered at the Nishi-Shichito Ridge, North-western Pacific Ocean.
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.
>>Link
ラキドニア科多毛類の新種ショウホラキドニアを正保海山の沈木より記載した。昨年行われた環境研究総合推進費の研究に基づくROVによる海山列海洋保護区モニタリングの基礎データとしての成果。
4.
Molines AT,Lemière J, Edrington CH, Hsu C-T, Steinmark IE, Suhling K, Goshima G, Holt LJ, Brouhard GJ, Chang F.
Physical properties of the cytoplasm modulate the rates of microtubule growth and shrinkage.
Dev Cell.
>>Link
細胞質の粘性により微小管の動態が影響を受けるという論文に、ヒメツリガネゴケの系で貢献した。
3.
Shirae-Kurabayashi M, Edzuka T, Suzuki M, Goshima G.
Cell tip growth underlies injury response of marine macroalgae
PLOS One.
>>Link
実験所周辺で採取した66種の海藻について切断応答を調べ、そのうち4種において切断面からの細胞伸長や核分裂の様子をライブイメージングで観察した。菅島臨海における海藻細胞分子生物学研究の第一歩となる論文。
2.
Goshima G.
Growth and division mode plasticity is dependent on cell density in marine-derived black yeasts
Genes to Cells.
>>Link
実験所の前で真菌類(カビ、酵母)を採集したところ、これまで研究によく用いられていた陸生のものとは異なり、細胞の密度に応じて成長や分裂の様式を変える種が複数見つかった。菅島臨海における海生真菌生物学研究の第一歩となる論文。
1.
Roeder AHK, Otegui MS, Dixit R, Anderson CT, Faulkner C, Zhang Y, Harrison MJ, Kirchhelle C, Goshima G, Coate JE, Doyle JJ, Hamant O, Sugimoto K, Dolan L, Meyer H, Ehrhardt DW, Boudaoud A, Messina C.
Fifteen compelling open questions in plant cell biology.
Plant Cell.
>>Link
植物細胞生物学で現在未解明の15の大きな問題が挙げられている。執筆者の一人として選ばれた五島は、細胞分裂面の決定機構について論じた。
2021年
Nakano H, Jimi N, Sasaki T, Kajihara H.Sinking Down or Floating Up? Current State of Taxonomic Studies on Marine Invertebrates in Japan Inferred from the Number of New Species Published Between the Years 2003 and 2020.
Zoological Science 39: Online first. >>Link
2003年以降に日本から新種記載された海産無脊椎動物のレビュー。日本における海洋無脊椎動物の分類学的研究は近年復活の兆しを見せているが、特定の分類群においては新しい分類学者の育成が課題であることが明らかになった。
Kanie S, Miura D, Jimi N, Hayashi T, Nakamura K, Sakata M, Ogoh K, Ohmiya Y, Mitani Y.
Violet bioluminescent Polycirrus sp. (Annelida: Terebelliformia) discovered in the shallow coastal waters of the Noto Peninsula in Japan.
Sci Rep. >>Link
能登から採集したPolycirrus属のフサゴカイが非常に短い波長で発光することを発見し、発光は免疫関連遺伝子の触手での発現と関連していることを明らかにした。発光は捕食者に対する防御の可能性を示した。
Jimi N, Hookabe N, Tani K, Yoshida R, Imura S.
The phylogenetic position of Branchamphinome (Annelida, Amphinomidae) with a description of a new species from the North Pacific Ocean
Zool Sci. >>Link
ウミケムシ科の中で非常に小さな体を持ち独特な形をしているBranchamphinome属を北太平洋から初めて発見し、新種として記載すると共に属の系統的な位置を決定することで特殊な形質の進化について議論した。
Tsuchiya K, Goshima G.
Microtubule-associated proteins promote microtubule generation in the absence of γ-tubulin in human colon cancer cells
J Cell Biol. . >>Link
>>プレスリリース(名古屋大学)
細胞の形作りや分裂に必須の細胞骨格・微小管が生み出される新しい機構をヒトの培養細胞を用いた実験で発見した。
Gomes Pereira S, Sousa AL, Nabais C, Paixão T, Holmes AJ, Schorb M, Goshima G, Tranfield EM, Becker JD, Bettencourt-Dias M.
The 3D architecture and molecular foundations of de novo centriole assembly via bicentrioles
Curr Biol. >>Link
コケ植物の精子の運動を担う鞭毛の形成機構に関する国際共同研究論文。
Goshima G.
Microtubule Nucleation Pathways
Encyclopedia of Biological Chemistry III (Third Edition). >>Link
細胞の形作りや分裂に必須の細胞骨格・微小管が生み出される分子機構についてのこれまでの知見を概説した。